| センチュリー行政書士・社労士事務所 |


| 【行政書士業務】 |
告訴状・告発状作成、相続関連手続、法人設立、建設業許可ほか各種営業許可申請、車庫証明・自動車登録、在留資格・VISA、内容証明作成、パスポート申請代行 など
|
| 【 社労士業務 】 |
就業規則作成・届出、36協定届作成・届出、労働保険・社会保険手続き、助成金申請、死傷病報告作成・届出、労働基準監督署対応、是正勧告書対応、各種労務相談 など
|

|
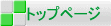  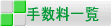 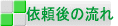 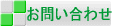 |
| CONTENTS |
厚生労働省の変な通達
|
賃金未払いは、皆さんご存じの通り、労働基準法違反です。
特に1ヶ月分以上の賃金未払いは、可罰性が認められるとして、労働基準監督署において検察庁に書類送検する対象事案となります。
さて、ここで問題なのが、「賃金未払い」事件を書類送検するに当たり、どの罪状で送検するかです。
労働基準法において賃金支払義務は第24条に規定されていることから、普通に考えれば、労働基準法第24条違反として送検するのが順当と言えます(実際、以前は労働基準監督署も賃金未払事件は労基法第24条違反で送検していました)。
ところが、10年ほど前に、厚生労働省がおかしな通達を出しました。
それは、「未払の結果、最低賃金額すら支払われていない場合は、最低賃金法違反で送検すべし」というものです。
例えば、ある月の賃金を一切支払っていない場合などには、当然「最低賃金分すら支払っていない」ことになり、労働基準法第24条違反ではなく、最低賃金法第4条違反として送検するよう、指示を出したわけです。
この厚生労働省の通達を受け、全国の労働基準監督署では、多くの賃金未払事件を労働基準法第24条違反ではなく、「最低賃金法第4条違反」として送検するようになりました。
|
| 【 厚生労働省の通達の問題点 】 |
しかし、この厚生労働省の通達には大きな問題点があります。
最低賃金法第4条は、
「使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない」
と規定されていますが、これはあくまで「所定賃金の設定を最低賃金以上にしなければならない」というものであり、約定賃金の額が最低賃金を下回ってはならないというのが法の趣旨であると解釈されます。
これは、最低賃金法が、「労働力の安売りを防止し、労働市場において適正な労働力の提供がなされることを目的とする」ための法律であることからも明らかです。
しかし、厚生労働省の通達によれば、約定賃金が最低賃金を上回っていても、結果として支払われた額が最低賃金額以下であれば最低賃金法違反として取り扱うことになります。
つまり、最低賃金法違反の構成要件である「約定賃金が最低賃金を下回っている」状態に該当しないにもかかわらず、最低賃金法違反として送検しなければならないこととなり、構成要件に該当しない以上、当然、罪に問うことはできなくなってしまいます。
実際、東京地方検察庁検事・司法研修所教官の見解としても、
「約定賃金が最低賃金額を上回っているかぎり、たとえ賃金不払いの結果として最低賃金額が支払われていない状態であったとしても、最低賃金法違反とはならない」
旨の見解が示されています(法務研究報告書第71集第6号第10章第3節第1)。
そのため、労働基準監督署が賃金未払事件を最低賃金法で送検するようになってからというもの、賃金未払事件は検察庁においてことごとく「不起訴」となり、賃金未払を犯した事業主が 「適切に略式起訴されて罰金を科せられる」 ということは無くなりました。
厚生労働省がこのような通達を出した理由は「労働基準法第24条違反よりも、最低賃金法第4条違反の方が罪が重い」という、きわめて短絡的な考えによるものですが、その結果、「賃金未払を犯しても、そもそも起訴されない」=「無罪放免」という、逆効果と言える状況を作り上げてしまったわけです。
|
| 【 厚生労働省で通達を作る者の資質 】 |
厚生労働省がこのような見当はずれの通達を出す背景には、厚生労働省の労働省サイドにおいて労働法関係の通達を出す者が、法律を体系的に学んだことのない者であるという事実があります。
多くの者が、行政に入って初めて法律に触れた者であり、その初めて触れた法律が労働基準法や労働安全衛生法と言った、いわゆる法律の中でも「枝葉」の部類に属する法律で、法律としてはかなり特殊な部類の法であるにもかかわらず、何しろ初めて接する法律なのでそれすらもわからずに「これが法律だ」という錯覚を起こし、法律的に体系的な解釈をおこなうすべを知らないまま、「読んで字のごとく」の解釈をおこなう結果、こういった見当違いの通達を出すことになるわけです。
厚生労働省が出す通達は、これ以外にも法的観点から明らかに間違った解釈の元に出されたものが非常に多く、これまでも多数の「見当はずれ」の通達が出されています。
全国の労基署において労働基準監督官に配布されている「労働基準法コンメンタール」という本があり、ほとんどの労働基準監督官はこの本に記載されている内容を鵜呑みにするのですが、この本に記載されている内容は、基本的にこれまでに厚生労働省によって出された通達をベースに、厚生労働省の労働省サイドの職員が編集しているもので、法的観点からこの本の内容を見ると、実に見当はずれの解釈が数多く記載されています。
にもかかわらず、この「労働基準法コンメンタール」をバイブルのように信奉している労働基準監督官が、3年間の実地研修だけで本省に行き、やがては通達を出すわけですので、まともな通達が出る方がおかしいと言えます。
|
|
|
|
| 【 関連項目 】 |
 告訴状・告発状作成コンテンツ 告訴状・告発状作成コンテンツ
 東京地検の告訴状の受理拒否問題 東京地検の告訴状の受理拒否問題
 警察が告訴状の受理を拒む理由 警察が告訴状の受理を拒む理由
 告訴状の作成の注意点 告訴状の作成の注意点
 告訴状の作成の費用 告訴状の作成の費用
 行政書士による告訴状の作成 行政書士による告訴状の作成
 告訴状と告発状 告訴状と告発状
 検察庁における告訴状の拒否 検察庁における告訴状の拒否
 告訴状にかかる警察の内部通達 告訴状にかかる警察の内部通達
 社労士による労働基準監督署への告訴状作成 社労士による労働基準監督署への告訴状作成
 警察庁の告訴状・告発状の受理にかかる通達 警察庁の告訴状・告発状の受理にかかる通達
 告訴状と被害届の違い 告訴状と被害届の違い
|
|
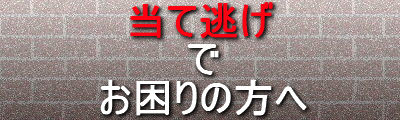
当て逃げの被害でお困りの方は、
当事務所にお任せ下さい。
当て逃げは卑劣な行為であり、被害を被った方としては
精神的にも我慢できない思いがあると思います。
しかし、警察は当て逃げについては
ほとんど動いてくれないのが現状です。
そんなときには、正式に告訴・告発の手続きを取りましょう。
(通常、当て逃げの場合は「告訴」ではなく「告発」になります)
卑劣な当て逃げ犯を見つけ出し、
罰を与えたいとお考えの方は、
正式に告訴状・告発状を作成して対処しましょう。
 当て逃げコンテンツへ 当て逃げコンテンツへ
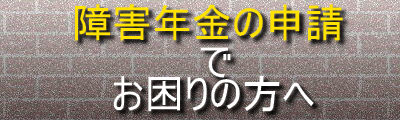
障害年金の申請でお困りの方は、
当事務所にお任せ下さい。
障害年金の申請には複数の書類を用意し、
「申立書」を作成しなければなりません。
「申立書」は傷病によっては非常に重用視されるもので、
傷害等級に認定を左右することも多々あります。
障害を持つ身でこれらの書類を整備し、
申請をおこなうことは困難を極めます。
お困りの方は、一度ご相談下さい。
 障害年金コンテンツへ 障害年金コンテンツへ
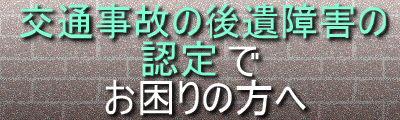
交通事故の後遺症・後遺障害の認定でお困りの方は、
当事務所にお任せください。
交通事故で後遺症が残っているにもかかわらず、
後遺障害の認定がなされない、あるいは
認定された障害等級が納得できない場合には、
異議申し立て(再請求)をおこないましょう。
 交通事故後遺障害コンテンツへ 交通事故後遺障害コンテンツへ
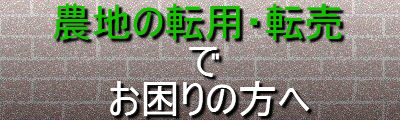
農地の転用・転売でお困りの方は、
当事務所にお任せ下さい。
使用していない農業用地は、他の用途に転用する、
あるいは他人に転売するなどといった活用方法があります。
しかし、農地の転用・転売をおこなうには、許可が必要です。
適切な手続きをとって、
休閑地となった農地を有効に活用しましょう。
 農地の転用・転売コンテンツへ 農地の転用・転売コンテンツへ
|
行政書士業務
※社労士(社会保険労務士)業務は
ここをクリック!
↓
「社労士(社会保険労務士)業務」へ |
■■■ 刑事手続 ■■■
|
 告訴状・告発状作成 告訴状・告発状作成
 告訴状・告発状の提出同行 告訴状・告発状の提出同行
 告訴状・告発状不受理時対応手続 告訴状・告発状不受理時対応手続
 検察審査会審査申立手続 検察審査会審査申立手続
|
■■■ 各種営業許可 ■■■
|
 建設業許可申請・更新 建設業許可申請・更新
 深夜酒類提供飲食店営業開始届 深夜酒類提供飲食店営業開始届
 産業廃棄物収集運搬許可・更新申請 産業廃棄物収集運搬許可・更新申請
 飲食店営業許可申請 飲食店営業許可申請
 風俗営業許可申請 風俗営業許可申請
 無店舗型性風俗特殊営業開始届 無店舗型性風俗特殊営業開始届
 建築士事務所登録 建築士事務所登録
 宅建業免許申請・更新申請 宅建業免許申請・更新申請
 一般貨物自動車運送事業許可申請 一般貨物自動車運送事業許可申請
 貨物軽自動車運送事業経営届出 貨物軽自動車運送事業経営届出
 自動車運転代行業認定申請 自動車運転代行業認定申請
 介護タクシー許可申請 介護タクシー許可申請
 居宅介護支援事業指定申請 居宅介護支援事業指定申請
 訪問介護事業指定申請 訪問介護事業指定申請
 福祉用具貸与・販売指定申請 福祉用具貸与・販売指定申請
 古物商許可申請 古物商許可申請
|
| ■■■ 法人設立・解散 ■■■ |
 株式会社・合同会社設立 株式会社・合同会社設立
 NPO法人設立 NPO法人設立
 一般社団法人設立 一般社団法人設立
 一般財団法人設立 一般財団法人設立
 法人解散 法人解散
|
| ■■■ 車庫証明など ■■■ |
 車庫証明・保管場所届 車庫証明・保管場所届
 自動車登録・名義変更 自動車登録・名義変更
|
| ■■■ 在留資格など ■■■ |
 外国人入国・在留手続 外国人入国・在留手続
 永住許可申請 永住許可申請
|
| ■■■ 内容証明など ■■■ |
 内容証明作成 内容証明作成
 クーリングオフ手続 クーリングオフ手続
 各種契約書作成 各種契約書作成
|
| ■■■ 相続・遺言 ■■■ |
 相続手続 相続手続
 遺言書作成 遺言書作成
 遺産目録作成 遺産目録作成
 資産調査/口座調査 資産調査/口座調査
|
| ■■■ 助成金等申請 ■■■ |
 各種助成金概要 各種助成金概要
 ものづくり・商業・サービス革新補助金申請 ものづくり・商業・サービス革新補助金申請
 創業促進補助金申請 創業促進補助金申請
 経営改善計画策定事業補助金申請 経営改善計画策定事業補助金申請
 経営革新計画申請 経営革新計画申請
 創造技術研究開発費補助金申請 創造技術研究開発費補助金申請
 地域新生コンソーシアム研究開発事業補助金申請 地域新生コンソーシアム研究開発事業補助金申請
 NEDO各種補助金・助成金申請 NEDO各種補助金・助成金申請
 IPA各種補助金申請 IPA各種補助金申請
 産業技術実用化開発事業費助成金申請 産業技術実用化開発事業費助成金申請
 環境活動補助金申請 環境活動補助金申請
 低公害車普及助成金制度申請 低公害車普及助成金制度申請
 CEV補助金 CEV補助金
 高齢者住宅改修費用助成金申請 高齢者住宅改修費用助成金申請
|
| ■■■ 農地転用許可・届出 ■■■ |
 農地転用許可・届出 農地転用許可・届出
 開発許可申請 開発許可申請
|
| ■■■ その他 ■■■ |
 交通事故後遺症/後遺障害等級認定サポート 交通事故後遺症/後遺障害等級認定サポート
 パスポート申請代行 パスポート申請代行
 銃砲刀剣類等所持許可申請 銃砲刀剣類等所持許可申請
|
|
社労士(社会保険労務士)業務
※行政書士業務はここをクリック
↓
「行政書士業務」へ |
| ■■■各種書類作成・届出■■■ |
 就業規則作成・届出 就業規則作成・届出
 36協定作成・届出 36協定作成・届出
 事業場外労働協定作成・届出 事業場外労働協定作成・届出
 適用事業報告作成・届出 適用事業報告作成・届出
 変形労働時間制協定届作成・届出 変形労働時間制協定届作成・届出
 預金管理状況報告作成・届出 預金管理状況報告作成・届出
|
| ■■■許認可申請■■■ |
 監視・断続的労働許可申請 監視・断続的労働許可申請
 宿日直許可申請 宿日直許可申請
 児童使用許可申請 児童使用許可申請
 最低賃金減額特例許可申請 最低賃金減額特例許可申請
 解雇予告除外認定申請 解雇予告除外認定申請
|
| ■■■各種協定書・契約書作成■■■ |
 変形労働時間制に関する協定書 変形労働時間制に関する協定書
 時間外・休日労働に関する協定書 時間外・休日労働に関する協定書
 事業場外労働に関する協定書 事業場外労働に関する協定書
 賃金控除に関する協定書 賃金控除に関する協定書
 雇用契約書 雇用契約書
|
| ■■■その他労務関係書類作成■■■ |
 労働条件通知書 労働条件通知書
 退職証明書 退職証明書
 解雇理由証明書 解雇理由証明書
 解雇通知書 解雇通知書
 労働者名簿 労働者名簿
 口座振り込み同意書 口座振り込み同意書
|
| ■■■労災保険加入手続■■■ |
 新規加入 新規加入
 特別加入 特別加入
 適用廃止 適用廃止
 名称変更・代表者変更 名称変更・代表者変更
|
| ■■■労災保険料の算定・申告■■■ |
 保険料算定・申告 保険料算定・申告
|
| ■■■労災申請手続■■■ |
 療養補償給付請求 療養補償給付請求
 指定病院等変更届 指定病院等変更届
 療養費用請求 療養費用請求
 休業補償給付請求 休業補償給付請求
 障害補償給付請求 障害補償給付請求
 遺族給付請求 遺族給付請求
 介護給付請求 介護給付請求
 二次健康診断等給付請求 二次健康診断等給付請求
 義肢等補装具費支給請求 義肢等補装具費支給請求
 訪問介護支給請求 訪問介護支給請求
 第三者行為災害届 第三者行為災害届
|
| ■■■安全衛生関係手続■■■ |
 労働者死傷病報告 労働者死傷病報告
 健康診断結果報告 健康診断結果報告
|
| ■■■社会保険加入手続■■■ |
 新規加入 新規加入
 適用廃止届 適用廃止届
|
| ■■■社会保険料の算定届■■■ |
 社会保険料算定・届出 社会保険料算定・届出
|
| ■■■社会保険給付申請手続■■■ |
 老齢年金給付申請 老齢年金給付申請
 遺族年金給付申請 遺族年金給付申請
 第三者行為災害による健康保険給付申請 第三者行為災害による健康保険給付申請
 障害年金給付申請 障害年金給付申請
|
| ■■■助成金等申請■■■ |
 各種助成金概要 各種助成金概要
 雇用調整助成金 雇用調整助成金
 労働移動支援助成金(再就職支援奨励金) 労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)
 労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援奨励金) 労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援奨励金)
 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金) 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)
 特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金) 特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)
 高年齢者雇用安定助成金 高年齢者雇用安定助成金
 障害者トライアル雇用奨励金 障害者トライアル雇用奨励金
 障害者初回雇用奨励金 障害者初回雇用奨励金
 中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金 中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金
 精神障害者等雇用安定奨励金 精神障害者等雇用安定奨励金
 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金
 地域雇用開発助成金 地域雇用開発助成金
 トライアル雇用奨励金 トライアル雇用奨励金
 中小企業労働環境向上助成金(団体助成コース) 中小企業労働環境向上助成金(団体助成コース)
 中小企業労働環境向上助成金(個別中小企業助成コース) 中小企業労働環境向上助成金(個別中小企業助成コース)
 キャリアアップ助成金 キャリアアップ助成金
 建設労働者確保育成助成金 建設労働者確保育成助成金
 障害者作業施設設置等助成金 障害者作業施設設置等助成金
 障害者福祉施設設置等助成金 障害者福祉施設設置等助成金
 障害者介助等助成金 障害者介助等助成金
 職場適応援助者助成金 職場適応援助者助成金
 重度障害者等通勤対策助成金 重度障害者等通勤対策助成金
 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
 両立支援等助成金 両立支援等助成金
 人材開発支援助成金 人材開発支援助成金
 障害者能力開発助成金 障害者能力開発助成金
 労働時間等設定改善推進助成金 労働時間等設定改善推進助成金
 職場意識改善助成金(職場環境改善コース) 職場意識改善助成金(職場環境改善コース)
 職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース) 職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)
 職場意識改善助成金(テレワークコース) 職場意識改善助成金(テレワークコース)
 中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金 中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金
 受動喫煙防止対策助成金 受動喫煙防止対策助成金
 退職金共済制度に係る新規加入等掛金助成金 退職金共済制度に係る新規加入等掛金助成金
 業務改善助成金 業務改善助成金
 65歳超雇用推進助成金 65歳超雇用推進助成金
 人事評価改善助成金 人事評価改善助成金
|
| ■■■その他■■■ |
 障害年金申請 障害年金申請
 給与計算 給与計算
 労働基準監督署対応 労働基準監督署対応
 労務相談 労務相談
|
|
ファイナンシャルプランナー業務
|
 ライフプランニング/資産設計 ライフプランニング/資産設計
 生命保険・損害保険見直し 生命保険・損害保険見直し
 遺産分割プランニング 遺産分割プランニング
|
|

個人事業を法人化することで
どのようなメリットがあるのでしょうか?
→ 法人化のメリット 法人化のメリット

経営者だけでなく、
ほかの従業員にとっても迷惑な、
たちの悪い労働者・・・
しかし、そんな労働者も
労基法で手厚く保護されているのです。
これら悪質な労働者に対して
合法的に対抗するには
どのようにすればよいのでしょう?
→ 悪質な労働者に対抗するために 悪質な労働者に対抗するために

日常生活や職場の中で、他人からの不当な行為により迷惑を被っていませんか?
迷惑行為の中には正式に刑事告訴することで解決できるケースが多々あります。
我慢したり泣き寝入りすることなく、
“悪いヤツ”には罰を与えましょう!
告訴状の作成は当事務所にお任せ下さい。
→ 刑事告訴活用術 刑事告訴活用術

センチュリー行政書士・社労士事務所では、
警察署への告訴状作成・提出について
全国対応致します。
被害の申立をしても
警察が動いてくれない場合には、
正式に告訴状を作成して対処しましょう。
→ 全国対応!警察署への告訴 全国対応!警察署への告訴
 告訴状・告発状関連特設ページ 告訴状・告発状関連特設ページ
|